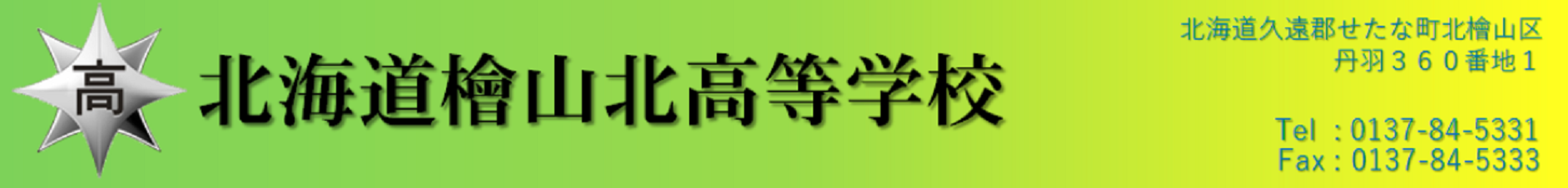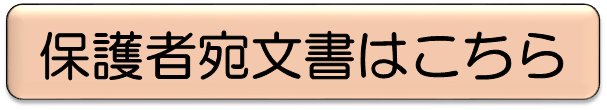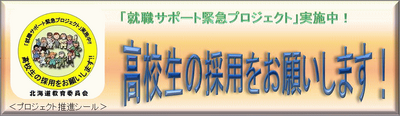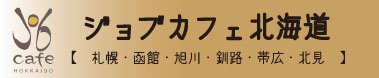2024年10月の記事一覧
【家庭科】「茶道体験・日本茶を楽しむ講座」を行いました②(生活教養)
10月16日(水)・23日(水)の2週にわたって行われた「茶道体験・日本茶を楽しむ講座」の「日本茶を楽しむ講座」の様子を掲載いたします。(茶道体験の様子は、①をご覧ください)
日本茶を楽しむ講座の講師は、函館市にある株式会社丸山園茶舗の代表取締役社長 井ヶ田嗣治さんです。
まずは12種類のお茶の違いを実際に飲んで体験しました。
お茶を淹れるために、まず自分たちで茶葉を計量します。なかなか4gぴったりにならず、難しそうです。
計量が終わると、水とお湯をそれぞれの容器に入れます。12種類のお茶を水・お湯で出したものをそれぞれ飲んだので、計24種類のお茶を飲んだことになります。
お湯と水の違いだけでも味や香りが違うのです。
生徒は「このお茶が好き」、「このお茶はちょっと苦い」、「落ち着く味がする」など色々な意見交換をしながらお茶を比べていました。
また、お茶屋さんがしている仕事の一つである、お茶の葉をお茶缶に詰める体験をしました。
皿とお茶缶だけでこぼさずにどうやって満タンに詰め込むのか…苦戦していました。井ヶ田さんに手本を見せてもらうと、鮮やかなプロの技に歓声が上がりました。
生徒からは「茶葉で入れたお茶がとても美味しかった。自分でも買ってお茶を入れてみたいと思った」、「習った入れ方でお茶を入れてあげたいと思った」などの感想が出ました。
こうして2週にわたって行われた「茶道体験・日本茶を楽しむ講座」が終了しました。この体験・講座を卒業後の生活でも生かして欲しいと思います。
【家庭科】「茶道体験・日本茶を楽しむ講座」を行いました①(生活教養)
10月16日(水)・23日(水)と2週にわたり、3年次の選択科目「生活教養」の科目で「茶道体験・日本茶を楽しむ講座」を行いました。
選択者28名が2つのグループに分かれて、それぞれの講座を1週ずつ受講しました。そこでまずは「茶道体験」の様子を掲載いたします。
茶道体験の講師は、本校茶道部の外部講師でもある佐々木佐代子先生です。
まずは茶道の歴史を知らなければなりません。日本史の授業にも出てくる人物の名前に生徒は頷き、メモを取りながらお話を聞いてます。
次にお茶席に招かれた際の作法について教えてもらいました。襖の開け方や畳の歩き方、お菓子の受け取り方を教わり、生徒は実際にやってみました。
そして、まずは自分でお茶を点てて飲んでみます。初めての体験に生徒は緊張した様子で、お茶を点てる道具を使っていました。
最後に2人一組になって相手をもてなすために、自分が点てたお茶を出す、というのを交代で行いました。
飲んでもらう人のことを思いながら点てるのが大事です。丁寧にもてなしてもらえて嬉しかったと生徒は言っていました。
「茶道」はお茶を点てる・飲むだけではなく、床の間に飾られた掛け軸や季節の草花、出されるお菓子や使われるお茶碗など様々な所にも気を配られています。こうした気配りで大事なことは、相手をもてなすための思いやりの気持ちだそうです。
卒業後は、こうした思いやりをもてる社会人となって頑張ってほしいです。
【家庭科】「1日防災学校」にてハイゼックス炊飯を行いました(生活教養)
10月2日(水)に北海道教育庁学校教育局生徒指導・学校安全課の事業である「1日防災学校」の一環として、3年次の選択科目「生活教養」でハイゼックス炊飯袋を使った炊飯を行いました。
ハイゼックス炊飯袋とは、高密度ポリエチレン製の熱に強い袋で、災害時に停電となっても、米と水・輪ゴムがあれば鍋でご飯が炊ける、という袋です。袋に米の量、水の量の目盛りが書いてあるため、計量カップ等がなくても簡単に炊飯ができます。
また、鍋で煮る時の水は雨水等でも大丈夫なので、災害時等はためておいた水と、炊飯用のきれいな水が最低限あれば炊くことができます。
今回は耐熱性のキッチンポリ袋を利用した湯せん調理にも挑戦し、アレンジ蒸しパンも作りました。
生徒は炊きあがったご飯をおにぎりにして、炊きあがり具合を確かめました。それぞれの水加減により、柔らかめのご飯、固めのご飯があったようです。
この他にも、災害時の避難先での生活についてなどを確認しました。
災害はいつ起こるか分かりません。いざという時に慌てないためにも、今回学んだことを忘れないでいて欲しいなと思います。
【家庭科】浴衣着装講座を行いました(生活教養)
9月11日(水)に3年生の選択科目「生活教養」の授業で、「浴衣着装講座」を行いました。
NPO法人 日本時代衣装文化保存会の方にお越しいただき、浴衣の着装や立ち居振る舞い、浴衣のたたみ方、五節供等を教えていただきました。
男女の浴衣の構造の違い、着付けの違いの講義を受けてから、男女に分かれて実際に自分で浴衣を着てみました。
生徒からは「浴衣を着る動作には昔からの日本の文化が影響していることが分かった」、「和装での振る舞いや座例など、一つ一つに意味があり、講義を聞いて勉強になりました」、「これからは自分で着付けたり、他の人に着付けできるように、教えてもらったことを覚えていたいです」と言った感想がありました。
ぜひ、この授業をきっかけに和服文化に興味を持ってもらえたら嬉しいです。